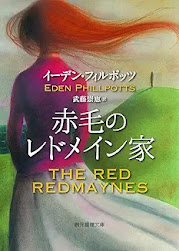昭和38年秋以降に起きた西口彰(根津巌)による連続殺人、詐欺事件を記録した本。これを基にした今村昌平監督の映画は有名である。この原著では映画にしなかった事件等の記述もある。例えば北海道まで行って詐欺を働いたとかがそうである。映画では脚色が当然あり、父親と妻の関係などは目につく映画での創作である。
それにしても最初の福岡県で二人を殺害する強盗殺人が起きたのは10月であり、年内のうちに殺人だけでも浜松で二人、東京で一人を殺している。その間、多くの詐欺窃盗を全国で行なっている。熊本県で少女が見抜き、逮捕されたのは明くる年の正月である。3ヶ月弱という間に恐るべき連続殺人を起こした。
この昭和38年という年は、3月に吉展ちゃん事件、5月に狭山事件が起こり、重大な犯罪が頻発している。西口事件は犠牲者が多かったが、早く解決したと言える。それにしても昭和38年というオリンピック前年の年は、マス・メディアは白黒テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、映画だけの時代であり、電話(もちろん固定)だって各家庭に行きわたっていなかった。個人のプライバシー(この言葉があったかどうかも不明)保護は今からすると、なかったような時代である。(文春文庫、2009(改訂新版))