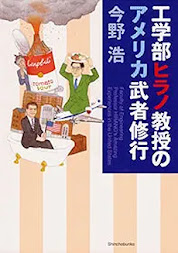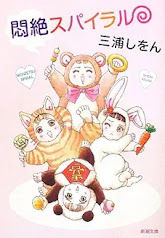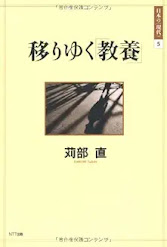ダリオ・アルジェント監督、伊仏、104分。主人公が夜道を歩いていると、後ろからつけてくる男がいる。主人公は男に詰め寄り、訳を問い質す。その際に男が持っていたナイフが男に突き刺さり、男は倒れる。死んだようだ。しかもいきなり遠くから灯りがついて、その様を撮影していたらしい。
主人公は気が重くなり妻には事件を話す。主人公は首を切られて処刑される夢を何度も見る。電話がかかり主人公を脅かす。実は死んだと思われていた男は実はトリックでそう見せかけただけで、生きていた。しかしその男も真犯人と思われる者に殺される。家の女中が真相に気がつくが、襲われ殺される。主人公は私立探偵を雇い調査される。同性愛の探偵で、やはり殺される。
従妹が家に来ており、これも真相を突き止め殺される。死んだ後、網膜に死ぬ直前の映像が残っているというので調べると四匹の蝿のようだ。この後、主人公は妻のペンダントを見る。するとそこには蝿が埋め込まれていた。被害者はこの動くペンダントを見て四匹の蝿が網膜に残ったのである。妻はなぜこのような凶行に及んだのか。夫への復讐のためである。妻は幼い日から父親に虐待を受け、復讐してやろうと思ったが父親が早死にしてしまう。妻に殺されそうになったが、知人が来て助かる。妻は車で逃げる。よそ見をしていた隙に大型車にぶつかる。大型車の端が車を突き、妻の首はちぎれて落ちる。